アジングに挑戦しようと思っている方にとって、ワームの「色」はどれほど重要なのか――
これは多くの人が一度は悩むポイントです。
特に、これから始める初心者にとっては、「何色を選べば釣れるのか」がわからないと思います。
この記事では、アジングワームの色で釣果が変わる理由を科学的な視点や、経験則を交えてわかりやすく解説します。
また、アジの色を見分け能力を解説し、なぜ特定の色が効きやすいのかを理解する手助けにもなるでしょう。
「アジングワームのカラーは釣果関係ない?」といった疑問を持つ人に対しても、実際のシチュエーションごとの反応や水質・光量の違いによる変化を踏まえた答えを紹介。
さらに、アジングワームの色選びの実践ガイドとして、実際の釣行でどう選び、どう使い分けるかの考え方も整理。
特に初心者が揃えておきたい3色についても明確にお伝えするので、ワーム選びで失敗したくない方はぜひ参考にしてみてください。
アジングワームの色で釣果が変わる理由

-
アジの色を見分け能力を解説
-
アジングワームのカラーは釣果関係ない?
-
濁りに強いワーム色とは?
-
アジング 朝 マズメ ワーム 色の選び方
-
夕マズメに有効な色の特徴
アジの色を見分け能力を解説
アジには、ある程度の色を識別する能力があります。
これは、夜行性の魚であるにもかかわらず、光や色に反応するという性質から分かっているようです。
まず、アジの目は「錐体細胞(すいたいさいぼう)」という色を感じる細胞が含まれており、昼間だけでなく、薄暗い環境でも色の違いをある程度見分けられる構造になっています。
ただし、人間のように細かな色彩の違いを見極められるわけではありません。
水中での光の届き方や濁り具合によっても色の見え方が大きく左右されるため、アジの色識別能力には限界があります。
「 魚たちは、私たちと同じ色を見ているのだろうか!? 魚を知りたければ、目を見ればいい!」
(グローブライトHPより)
例えば、クリアカラーとグロー系(発光系)のワームでは、明暗の違いや反射の仕方が異なるため、アジがそれを識別して行動に変化を見せることがあります。
一方で、赤とピンクといった似たような色味は、アジにとって大差ない可能性が高いです。
このように考えると、アジは色の違いを「完全に認識」しているわけではなく、「見た目の明るさや発光の有無」などを感知していると考えるほうが自然です。
そのため、アジングでは色そのものよりも、光の透過度や視認性の方が釣果に影響することもあります。
つまり、アジにはある程度の色の判別能力がありますが、それは限定的であり、明暗の差や発光特性の方が重要な判断材料になっているといえるでしょう。
※ただし、アジの色覚に関する研究はまだ完全ではなく、今後の研究によってさらに詳細な情報が明らかになることが期待されます。
アジングワームのカラーは釣果関係ない?
アジングで使用するワームのカラーについて、「釣果には関係ないのでは?」と感じる人もいますが、状況によっては関係性があるといえます。
釣果に直結するのは、実は「カラー」そのものではなく、状況に応じた「見え方」です。
つまり、ワームの色がどう見えるかが重要なのであって、色の好みそのものがアジにあるとは限りません。
例えば、日中で水がクリアな状態なら、ナチュラル系カラー(クリアやベイトに近い色)が目立ちすぎず、自然な誘いができます。
一方、濁りが強い日やナイトゲームでは、グローやチャート系のような視認性の高いカラーが効果を発揮しやすくなります。
ただし、まったく同じタイミング・同じ場所で、異なるカラーのワームを使って釣果に大差が出るケースは少ないという点も覚えておくべきです。
釣れないときに色を変えても状況が改善しないのは、そもそも魚がいないか、食い気がない、アジのいるレンジで誘えていない、といった別の要因が関係している場合が多いからです。
このように考えると、アジングワームのカラーは「釣果に直接関係があるわけではない」が、「状況に合わせて最適化することで釣果を引き出せる要素の一つ」だといえるでしょう。
したがって、カラーは重要ではないというよりも、釣果を左右する複数の要素の一部にすぎない、という考え方が適しています。
濁りに強いワーム色とは?
水の濁りが強い状況では、アピール力のある色を選ぶことが効果的です。
というのも、濁った水中では視界が悪くなり、アジがワームを視認しにくくなるからです。
そのため、目立つ色、具体的には「グロー(夜光)」「チャート(蛍光黄緑)」「ピンク」などの派手なカラーが有効とされています。
これらの色は水中で光を反射したり、輪郭がはっきり見えるため、アジの注意を引きやすくなります。
例えば、雨の後や河川が絡むポイントなど、濁りが強いエリアでは、ナチュラル系よりも派手色のほうが釣果に結びつくケースが多いです。
逆に、透明度の高い水質では、これらの色がプレッシャーを与える場合もあるため、適材適所で使い分けることが重要です。
このように考えると、濁り対策としては「光とコントラストで目立たせる色」を基準に選ぶのが効果的だといえます。
朝マズメに有効な色の選び方
朝マズメは、日が昇る直前から明るくなり始める時間帯です。
この時間帯はアジの活性が高く、釣果が伸びやすい一方、光量の変化が大きいためワームの色選びが重要になります。
まず、マズメの初期はまだ薄暗いため、グロー(夜光)やUVカラーなどの視認性が高い色が有効です。
これにより、アジに対して強いアピールが可能になります。光量が増すにつれて、パール系やクリア系のナチュラルカラーに切り替えると、違和感を与えにくくなります。
例えば、日の出前にグロー系で反応が良かったとしても、明るくなるにつれてアタリが遠のくようなら、クリアや白系に変更して様子を見ましょう。
逆に、光量が足りないのにクリア系を使ってしまうと、アジがワームを見つけられないことがあります。
このように、朝マズメのワーム選びでは「時間帯による光量の変化」に合わせて色を使い分けることがポイントです。
関連記事
「アジングで朝マズメの釣果アップ完全ガイド」
夕マズメに有効な色の特徴
夕マズメは、日が沈む前後の薄暗い時間帯で、アジの活性が一時的に上がるタイミングです。
この時間帯では、光量が徐々に減っていくため、視認性の高いカラーを選ぶことで釣果に差が出やすくなります。
有効とされるのは「グロー(夜光)」や「チャート(蛍光色)」「オレンジ」「ピンク」など、暗がりの中でも目立ちやすく、シルエットのはっきり出る色です。
これらのカラーは、太陽光が弱まるにつれてワームの存在を際立たせる効果があり、アジに発見されやすくなります。
また、UVカラー(紫外線に反応する塗料を使った色)もこの時間帯に力を発揮します。
人間の目にはわかりにくくても、紫外線を受けると独特の光を放ち、水中でのアピール力が高まるためです。
このように、夕マズメでは「光を受けて目立つ」あるいは「シルエットがはっきり出る」カラーが釣果アップにつながりやすくなります。
アジングワームの色選びの実践ガイド

-
初心者が揃えておきたい3色
-
点発光の有効性
-
グローやUVカラーの有効性を検証
-
シチュエーション別カラー選定の基本
-
光量と水質が与える影響とは
初心者が揃えておきたい3色
アジングをこれから始める人にとって、どのワームカラーを選べばよいか迷うのは当然です。
そこで、状況ごとに使い分けしやすく、基本として持っておきたい3つの色を紹介します。
まず押さえておきたいのが「クリア系カラー」です。透明感があるため、澄んだ海や日中の明るい時間帯に自然に溶け込み、アジの警戒心を抑えて口を使わせやすい特徴があります。
実績も高く、プレッシャーのかかる場面でも安定した効果が期待できます。
次におすすめするのは「グロー系(夜光)」です。
これは夜釣りや濁った水中、マズメ時のように光が少ない状況で力を発揮します。
発光することでワームの存在をアジにしっかりアピールできるため、視認性の面でも非常に有効です。
最後に「チャートカラー」または「ピンク」などの蛍光色系。これらは明るく目立つため、アジの活性が高い時や濁りのある状況で使いやすく、遠くの個体にも強くアピールできます。
この3色を揃えておけば、多くの釣行シーンをカバーすることができ、初めてのアジングでも安心して臨めます。
どれを選ぶか迷ったときは、まずこの基本の3色を基準に考えてみると良いでしょう。
関連記事
「アジングワームのサイズ選びで釣果アップの秘訣」
点発光の有効性
点発光タイプのワームは、特に低活性時や光量の少ない状況で効果を発揮しやすいとされています。
理由は、ワーム全体が光るのではなく、一部分だけが発光することで、アジの視覚を刺激しやすくなるためです。
アジは常に神経質で警戒心が強く、派手すぎるルアーには見向きもしないこともあります。
このようなとき、点発光のような「控えめなアピール」は、違和感を与えにくく、自然に近い印象を持たせることができます。
例えば、ワームのテールやヘッドだけが発光するタイプを使えば、全体的にナチュラルなシルエットを保ちながら、特定の部位で存在感を示せます。
こうしたバランスは、プレッシャーの高いポイントやスレたアジを攻略する際に役立ちます。
ただし、状況によっては全体が発光するワームのほうが目立って効果的なこともあるため、点発光タイプが万能というわけではありません。
複数の種類を持ち、状況に応じて使い分けることが重要です。
グローやUVカラーの有効性を検証
グロー(夜光)やUV(紫外線反応)カラーは、アジングにおいて一定の効果があるとされています。
特に光量が少ない時間帯や、水の濁りが強い場面での視認性向上に役立ちます。
グローカラーは暗闇でも蓄光によってぼんやりと発光し、アジの視界に入りやすくなるため、夜間や深場のアジングでは多用されます。
一方で、UVカラーは太陽光や月光などに反応し、人の目では見えにくい反射を生み出すため、日中や曇天の場面でさりげなくアピールできるのが特長です。
例えば、曇り空の朝マズメなど、光量が中途半端な環境では、グローほど強くなく、ナチュラルなUVカラーが効くケースがあります。
逆に、真っ暗なナイトゲームでは、発光するグローの方が目立ちやすく、集魚効果が高まります。
ただし、グローやUVはあくまで視認性を高めるための手段であり、それだけで釣果が劇的に変わるわけではありません。
水の透明度やアジの活性、プレッシャーの程度などを見極めたうえで選ぶことがポイントです。
シチュエーション別カラー選定の基本
アジングでは、釣れるかどうかを左右する要素のひとつがワームの色選びです。
状況に応じたカラー選定ができれば、より多くのアジに口を使わせることが可能になります。
基本としては、「水質」「光量」「時間帯」の3つを軸に考えるのが効果的です。
例えば、水が澄んでいて日中のように明るい時間帯であれば、ピンクやクリア系、ホワイトなどの「ナチュラルカラー」が警戒心を与えにくく、スレたアジにも有効です。
一方、朝マズメや夕マズメのように薄暗くなる時間帯や、曇天・夜間など光量が少ない場面では、チャートやオレンジ、グロー系などの「アピールカラー」が活躍します。
アジの視界に入りやすく、ワームの存在をより強調することができるからです。
また、潮の濁りが強い日や雨のあとなどは、視界が制限されるため、やや強めの色(グロー、点発光、ソリッドカラー)を中心に選ぶとよいでしょう。
水が緑や茶色に濁っているような状況では、白や蛍光色が特に目立ちやすくなります。
つまり、ワームのカラーは「釣れる色」ではなく、「その時・その場所で見える色かどうか」が選定のポイントとなります。
釣行前に現地の天候や水の色を確認する習慣をつけると、失敗のない色選びにつながります。
光量と水質が与える影響とは
アジングにおける光量と水質の影響は、想像以上に大きな意味を持ちます。
これらはアジの視界を左右するため、ワームカラーの見え方にも直結します。
まず光量についてですが、明るい状況ではワームの色がはっきり見えるため、透明感のある色やパール系、ブルーやグリーンといった水に馴染みやすい色など、ナチュラルなカラーが向いています。
逆に、光が少ない場面では、グローやUV、チャート系など、自己発光または光反射に優れた色が効果的です。
水質に関しては、水の透明度が高いほどアジの視認力が上がり、ワームの不自然な色や動きが見抜かれやすくなります。
そのため、クリア系やスモークカラーなど、できるだけ自然に溶け込む色を選ぶのが無難です。
逆に濁っているときは、水の色に対して目立つワームを使わなければ、存在に気づかれにくくなります。
例えば、茶色っぽく濁った水では、明るいオレンジや白、蛍光グリーンなどが効果的です。
一方、緑がかった濁りなら、ピンクや紫などの中間色も選択肢になります。
こう考えると、光量と水質はカラー選びの前提条件とも言える要素です。
釣果を上げたいなら、天候や潮の状況を軽視せず、その日の水と光を見てからワームカラーを決めることが大切です。
アジング ワーム 色の選び方と釣果への影響まとめ
-
アジには光の明暗や発光の有無を見分ける視覚がある
-
色よりもワームの「見え方」が釣果に関係する
-
濁りが強い日はグローやチャート系カラーが有効
-
朝マズメは光量に応じてグローからナチュラル系に切り替える
-
夕マズメは視認性の高いオレンジやピンクが効果的
-
初心者はクリア系・グロー系・チャート系を揃えると対応しやすい
-
点発光タイプは低活性時に違和感を与えにくい
-
グロー系はナイトゲームや深場に強いアピール力を持つ
-
UVカラーは曇天や朝夕の中間光量下で自然にアピールできる
-
水質が澄んでいるときは透明感のある色が有効
-
水が濁っているときは輪郭が目立つ明色が必要
-
アジングでは時間帯や天候に応じたカラーの切り替えが重要
-
魚がいない・レンジが違う場合は色を変えても釣果に影響しない
-
ワームのカラーは単独ではなく、状況との組み合わせで効果を発揮する
-
カラー選定前に現場の光量・水の色を確認する習慣が釣果に直結する









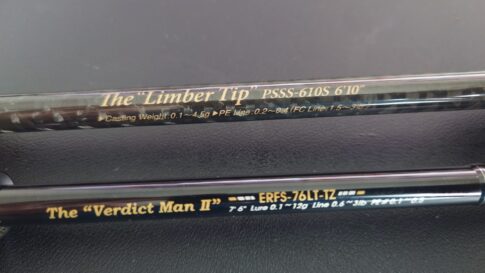






アジが色を識別する能力とその限界
釣果に影響するワームカラーの選び方
状況別に有効なワームカラーの特徴
初心者におすすめの基本的な3色選定方法