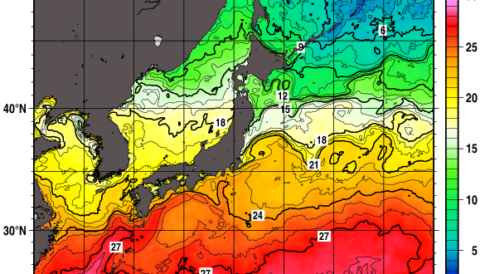夜アジング完全攻略!釣果を伸ばす13のコツ
アジングは夜が釣れるとよく耳にしますが、なぜ夜釣りなのか?と疑問に思ったことはありませんか。
アジングを夜に楽しむ上で、場所選びや夜に強いアジングワームの選び方、常夜灯なしのポイント攻略など、知っておきたいことは沢山あります。
特に、ワームの色や適切な仕掛け、アジのいるレンジの探り方は釣果を大きく左右する重要な要素です。
この記事では、夜のアジングで釣果を上げるための基本から応用テクニックまで、あなたの疑問を解消し、次の釣行を成功に導くための全てを解説します。
- 夜にアジが釣れる理由と最適な場所選びがわかる
- ナイトゲームに効果的な仕掛けやワームの選び方が身につく
- 釣れない状況を打破する具体的なテクニックが学べる
- 安全に夜アジングを楽しむための必須知識が得られる
夜アジングを成功させる基本
- そもそもなぜ夜釣りなのか?
- 釣果を左右する夜の場所選び
- ナイトゲームの基本となる仕掛け
- 夜に強いワームの色と選び方
- 安全に必須なヘッドライトとは
- 集魚灯はアジングに有効か?
- 釣果に直結する潮と時間帯の選び方
そもそもなぜ夜釣りなのか?

アジングが夜に盛んに行われるのには、明確な理由があります。
アジ自体は昼行性で夜行性ではありませんが、夜間は日中よりも岸に寄り、捕食活動が活発になる傾向があるのです。
主な理由として、アジの餌となるプランクトンや小魚が、常夜灯の光に集まることが挙げられます。
餌が集まる場所には、それを捕食するアジも自然と集まってくるため、日中に比べてアジの居場所を特定しやすくなります。
これが、「夜のアジングは釣りやすい」と言われる最大の要因です。
また、夜間は釣り人の数が減るため、ポイントへのプレッシャーが低くなるのもメリットの一つ。
日中のハイプレッシャーな状況では警戒心の高いアジも、夜になると比較的ルアーに反応しやすくなります。
このように、アジの習性と釣り場の環境の両面から、夜はアジングにとって絶好の時間帯となるのです。
夜釣りのメリットまとめ
- 常夜灯周りに餌とアジが集まり、ポイントを絞りやすい
- 日中よりもアジの警戒心が薄れる傾向にある
- 釣り人が少なく、プレッシャーが低い環境で釣りができる
釣果を左右する夜の場所選び

夜のアジングで釣果を出すためには、ポイント選びが非常に重要です。
闇雲に竿を出すのではなく、アジが集まりやすい条件を備えた場所を狙うことが成功への近道となります。
常夜灯のある漁港・港湾
最も定番で、初心者にもおすすめなのが常夜灯のあるポイントです。
前述の通り、常夜灯の光はプランクトンを寄せ、それを目当てにアジが集まります。
特に狙い目なのは、光が当たっている場所と暗い場所の境目である「明暗部」です。
アジは明るい場所で餌を探し、危険を感じると暗い場所に隠れる習性があるため、明暗部は絶好の待ち伏せポイントになります。
潮通しの良い堤防の先端
堤防の先端部分は潮の流れが良く、回遊してくるアジの通り道になりやすい一級ポイントです。
潮の流れが堤防にぶつかることでヨレ(流れの変化)が生まれ、そこにプランクトンが溜まりやすくなります。
常夜灯がなくても、このような地形変化のある場所は大型のアジが回遊してくる可能性が高く、積極的に狙う価値があります。
テトラ帯
テトラ帯もアジが好むポイントの一つです。
テトラ自体がストラクチャー(障害物)となり、アジの隠れ家や回遊ルートになります。
ただし、夜間のテトラ帯は足場が悪く危険が伴います。釣行する際は、滑りにくい靴やライフジャケットを必ず着用し、安全には最大限の注意を払ってください。
場所選びの注意点
人気のポイントは釣り人が多い場合があります。
先行者がいる場合は挨拶をし、十分な距離を取るなどマナーを守って釣りを楽しみましょう。
また、漁港によっては夜間の立ち入りが禁止されている場所もあるため、事前に確認が必要です。
ナイトゲームの基本となる仕掛け
夜のアジングでは、状況に応じて様々な仕掛け(リグ)が使われますが、基本となるのは「ジグヘッド単体リグ(ジグ単)」です。
これは、オモリと針が一体化したジグヘッドにワームをセットするだけのシンプルな仕掛けで、手軽さと感度の良さが魅力です。
ジグヘッドの重さは、1g前後を基準に考えましょう。
潮の流れが緩やかで水深が浅い場所では1g以下の軽いものを、潮が速い場所や水深があるポイントでは1g以上の重いものを選びます。
軽いジグヘッドほど、ワームをゆっくりと沈ませる(フォールさせる)ことができ、活性の低いアジにもじっくりとアピールできます。
まずは1gのジグヘッドから始めて、アタリがなければ0.8g、0.6gと軽くしたり、逆に風が強くて操作しにくい場合は1.2g、1.5gと重くしたりと、状況に合わせて調整していくのが釣果アップのコツですよ。
ジグ単で届かないような遠くのポイントを狙いたい場合は、「フロートリグ」や「キャロライナリグ」といった遠投向けの仕掛けも有効です。
これらのリグは、ジグ単よりも重いオモリを使うことで飛距離を稼ぐことができます。
| リグの種類 | 特徴 | 得意な状況 |
|---|---|---|
| ジグヘッド単体(ジグ単) | 最もシンプルで感度が高い。手返しが良い。 | 近距離戦、常夜灯周り、基本的な状況全般 |
| フロートリグ | ウキ(フロート)を使い、軽いジグヘッドを遠投できる。表層をゆっくり探るのに適している。 | 遠浅のポイント、沖の表層を狙う場合 |
| キャロライナリグ | 中通しオモリを使い、遠投性能が高い。ボトム(底)や中層を探りやすい。 | 遠距離のポイント、水深のある場所 |
夜に強いワームの色と選び方

ワームのカラーは、夜のアジングにおいて釣果を大きく左右する要素です。
アジは色を識別する能力があると言われており、状況に合ったカラーを選ぶことが重要になります。
基本的には、「クリア系」「グロー系」「ソリッド系」の3種類を揃えておくと、様々な状況に対応できます。
クリア系
透明感のあるカラーで、プランクトンやアミなどの小さなベイトを捕食している場合に特に有効です。
常夜灯の光が強い場所や月明かりが明るい夜、アジの警戒心が高い(スレている)状況で効果を発揮します。
ラメが入っているものは、光を反射してアピール力をプラスできます。
グロー(夜光)系
光を蓄えて自ら発光するカラーで、ナイトゲームの定番です。
常夜灯のない真っ暗な場所や、潮が濁っている状況でアジにワームの存在を強くアピールできます。
光りすぎると逆に警戒されることもあるため、ぼんやり光る程度のものがおすすめです。
ソリッド系
ブラック、ピンク、チャート(黄緑系)など、シルエットがはっきりと出る不透明なカラーです。
常夜灯の明かりの下でワームの輪郭を際立たせたい場合や、アピール力を高めたい時に有効です。
特にブラックは、どんな光量でもシルエットがはっきりするため、ナイトアジングでは欠かせないカラーの一つです。
ワームのサイズと形状
ワームのサイズは2インチ前後が標準です。
アジの活性や捕食しているベイトの大きさに合わせて、1.5インチの小さいものや2.5インチの大きいものを使い分けましょう。
形状は、細長い「ピンテール」や「ストレート」タイプが基本で、ナチュラルな波動でアジを誘います。
安全に必須なヘッドライトとは
夜釣りにおいて、ヘッドライトは安全を確保するための必須アイテムです。
常夜灯がある場所でも、手元は自分の影で暗くなりがち。
仕掛けを結び直したり、釣れた魚から針を外したりといった作業を安全かつスムーズに行うために、必ず用意しましょう。
ヘッドライトを選ぶ際は、以下のポイントをチェックすると良いでしょう。
明るさ(ルーメン)
釣りに使用する場合、200ルーメン以上の明るさがあると安心です。
明るいほど遠くまで照らすことができ、足場の確認や周囲の状況把握がしやすくなります。
電源の種類
電源は大きく分けて「乾電池式」と「充電式」があります。
乾電池式は、電池が切れてもコンビニなどで手軽に入手できるのがメリット。
充電式は、ランニングコストが安く、USBで充電できるモデルも多いため便利です。
予備の電池やモバイルバッテリーを持っていくと、万が一の時も安心です。
赤色ライト機能
多くの釣り用ヘッドライトには、白色光の他に赤色光モードが搭載されています。
赤色の光は魚に警戒心を与えにくいとされており、水面近くで作業する際に魚を散らしてしまうのを防ぐ効果が期待できます。
手元を照らすだけなら赤色ライトで十分な場合も多いので、積極的に活用しましょう。
ヘッドライト使用時のマナー
ライトの光を直接人の顔に向けたり、不必要に水面を照らし続けたりするのはマナー違反です。
特に水面を照らす行為は、魚を散らしてしまうだけでなく、他の釣り人の迷惑にもなります。周囲への配慮を忘れずに使用しましょう。
集魚灯はアジングに有効か?
集魚灯は、水中に光を照らして魚を寄せるアイテムです。
イカ釣りなどでよく使われますが、アジングにおいても非常に有効な場合があります。
集魚灯の最大のメリットは、常夜灯がない真っ暗なポイントでも、自分でアジが寄る場所を作り出せることです。
光にプランクトンが集まり、それを食べにアジが集まるという、常夜灯と同じ効果を人工的に生み出します。
特に、普段は人が攻めないような場所で使うと、思わぬ爆釣に繋がる可能性があります。
一方で、デメリットも存在します。
集魚灯の光が強すぎると、アジが光に集まったマイクロプランクトンに夢中になり、ルアー(ワーム)に全く反応しない「プランクトンパターン」に陥ってしまうことがあります。
また、自治体によっては集魚灯の使用が禁止されているエリアもあるため、事前の確認が必須です。
集魚灯の効果的な使い方
集魚灯を使う際は、光が当たっている中心部だけでなく、その周りの薄暗い場所や明暗の境目を狙うのが効果的です。
光に直接集まっているアジよりも、その周辺でベイトを待ち構えている高活性なアジを狙うことができます。
集魚灯は強力な武器になりますが、万能ではありません。
メリットとデメリットを理解した上で、ルールとマナーを守って活用することが大切ですね。
釣果に直結する潮と時間帯の選び方
アジは回遊魚であり、その動きは潮の流れに大きく影響されます。
そのため、夜アジングで釣果を上げるには、潮の動きと時間帯を意識することが非常に重要です。
潮の動きを読む「タイドグラフ」
釣行前には、必ず「タイドグラフ(潮汐表)」を確認しましょう。
スマートフォンアプリやウェブサイトで簡単に見ることができます。タイドグラフを見れば、満潮・干潮の時間や潮位の変化が分かり、釣りの計画を立てるのに役立ちます。
一般的に、魚の活性が上がるのは「潮が動いている時間帯」です。
潮が止まっている満潮・干潮の前後(潮止まり)はアタリが遠のき、潮が動き始める「上げ三分・下げ七分」といったタイミングで釣れ始めることが多いです。
特に、満潮や干潮からの潮が切り替わるタイミングは、大きなチャンスとなり得ます。
ゴールデンタイム「マズメ時」
日の出前と日没後の薄暗い時間帯は「マズメ時」と呼ばれ、魚の捕食活動が最も活発になるゴールデンタイムです。
夜のアジングでは、日没後の「夕マズメ」を狙うのがセオリー。
この時間帯は、日中の隠れ家からアジが出てきて積極的に餌を探し始めるため、数・型ともに期待できます。
釣行スケジュールを組む際は、このマズメ時を絡めるのがおすすめです。
大潮は必ずしも釣れるわけではない?
潮の干満差が最も大きい「大潮」は、潮がよく動くため釣りに良いとされています。
しかし、流れが速すぎるとアジが岸に寄りにくかったり、仕掛けのコントロールが難しくなったりすることもあります。
逆に潮の動きが緩やかな「小潮」や「長潮」の方が、ポイントにアジが留まりやすく釣りやすい、というケースも少なくありません。
タイドグラフを参考にしつつ、実際の現場の状況に合わせて判断することが大切です。
夜アジングで釣果を伸ばす実践テク

- アジがいるレンジの見つけ方
- 常夜灯なしポイントの攻略法
- ラインが見えない時の解決策
- どうしても釣れない時の対処法
- 月明かりや風が釣果に与える影響
- 快適な夜アジングを楽しむために
アジがいるレンジの見つけ方
アジは常に同じ水深(レンジ)にいるわけではなく、時間や状況によって表層からボトム(底)まで、泳ぐ層を変えます。
その日のアジがいるレンジをいかに早く見つけ出すかが、釣果を伸ばす鍵となります。
最も基本的なレンジの探し方は「カウントダウン」です。
これは、仕掛けをキャスト(投げて)着水させてから、心の中で秒数を数えて任意の深さまで沈めるテクニックです。
カウントダウンの手順
- 仕掛けをキャストし、着水と同時に秒数を数え始める(1, 2, 3…)。
- まずは5秒数えて(5カウント)、そこから釣りを開始する。
- アタリがなければ、次のキャストでは10カウント、その次は15カウントと、徐々に沈める時間を長くしていく。
- アタリがあったカウントが、その時のアジがいるレンジの目安となる。
例えば、15カウントでアタリが連発した場合、その周辺のレンジ(13〜17カウントなど)を重点的に探ることで、効率よく釣果を重ねることができます。
アタリがなくなったら、アジのレンジが変わった可能性があるので、再び表層からカウントダウンをやり直して探りましょう。
ジグヘッドの重さが1gの場合、おおよそ「1カウント=30cm」沈むとイメージしておくと、水深を把握しやすくなりますよ。
ただし、これは潮の流れやラインの太さで変わるので、あくまで目安として考えてくださいね。
常夜灯なしポイントの攻略法

常夜灯のない真っ暗なポイント、通称「闇アジング」は、一見すると難易度が高そうに思えます。
しかし、常夜灯周りのように釣り人のプレッシャーが低く、警戒心の薄い大型のアジが潜んでいる可能性が高い、魅力的なフィールドでもあります。
闇アジングで最も重要なのは、「潮通しの良さ」です。
常夜灯というアジを集める要素がない分、回遊してくるアジをいかに足止めするかがポイントになります。
堤防の先端やテトラ帯、ミオ筋(船の通り道)周りなど、潮の流れに変化が生まれる場所を探しましょう。
目に見える目標物がないため、一つの場所に固執せず、広範囲を手返し良く探っていく「ランガン(Run & Gun)」スタイルが基本となります。
少し投げて反応がなければ移動、を繰り返して活性の高いアジの群れを探し当てます。
仕掛けは、遠投も考慮してジグ単だけでなく、キャロライナリグやフロートリグも準備しておくと、攻略の幅が広がります。
闇アジングのワーム選び
闇アジングでは、アピール力の高いワームが有効です。
グロー(夜光)系や、シルエットがはっきり出るソリッド系のブラックなどが実績の高いカラー。
また、ワームの波動で存在を知らせるために、少し大きめのサイズや、リブの深いワームを試してみるのも良いでしょう。
ラインが見えない時の解決策
夜釣りでは、細い釣り糸(ライン)がほとんど見えません。
どこまで巻いたか分からずにジグヘッドを竿先に巻き込んでしまったり、ライントラブルに気づかなかったりするのは、ナイトアジングでよくある悩みです。
しかし、いくつかの工夫でこの問題は解消できます。
視認性の高いラインを選ぶ
ラインには様々な色がありますが、夜間でも比較的見やすいピンクやイエローといった蛍光色のラインを選ぶのが最も簡単な対策です。
特にエステルラインやPEラインはカラーバリエーションが豊富なので、視認性の高いものを選びましょう。
ワームやジグヘッドで判断する
グロー(夜光)系のワームを使えば、ぼんやりとした光でワームの位置を把握しやすくなります。
また、仕掛けを回収する際は、竿先に集中し、ジグヘッドがガイドに当たる「カツッ」という小さな感触で巻き上げるのを止めるように意識するのも一つの方法です。
ショックリーダーの結束部で判断する
メインラインとショックリーダー(先糸)の結束部を、ガイドを通る際に「コツコツ」と感触が伝わるように少しだけ大きめに作っておく方法もあります。
結束部がガイドを通った感触があれば、「あと少しで竿先だ」と判断できるため、巻き込み防止に役立ちます。
ラインのたるみに注意
ラインが見えないと、意図せずラインがたるんでしまい、アジの小さなアタリを見逃す原因になります。
またキャスト後も着水時にしっかりとサミングすることも忘れてはいけません。
ラインがたるんだままリールを巻いてしまうと、「ぴょん吉」となり、ライントラブルの元になります。
特に暗い中のアジングの場合は、ぴょん吉に気づきにくいので注意が必要です。
常にラインが張りすぎず、緩みすぎない状態をキープするよう心がけることが、釣果アップに繋がります。
どうしても釣れない時の対処法

「アジがいるはずなのに、全くアタリがない…」そんな厳しい状況に陥ることも少なくありません。
そんな時は、粘り強く同じことを繰り返すのではなく、積極的に変化をつけていくことが状況を打開する鍵となります。
アクションを変える
基本的なリフト&フォールで反応がなければ、アクションに変化を加えてみましょう。
竿先を細かく震わせる「シェイク」を入れたり、ただゆっくりとリールを巻くだけの「ただ巻き」を試したりします。
時には、ボトム(底)まで沈めてしばらく放置する「ボトムステイ」が効くこともあります。
ワームのローテーション
カラー、サイズ、形状をとことん変えてみましょう。
クリア系がダメならグロー系、グロー系がダメならソリッド系と、系統の違うカラーを試します。
サイズを1.5インチに落としてみたり、逆に2.5インチに上げてアピールを強めたりするのも有効です。一つのワームに固執せず、引き出しを総動員しましょう。
リグやジグヘッドの重さを変える
ジグヘッドの重さを変えるだけで、フォールスピードや沈む角度が変わり、アジの反応が劇的に変わることがあります。
0.1g単位で重さを変えて、その日のアタリパターンを探ります。ジグ単に反応がなければ、フロートリグやキャロライナリグ、さらにはメタルジグなどに変更して、全く違うアプローチを試すのも一つの手です。
「釣れない時こそ、普段やらないことを試すチャンス」と捉えましょう。
試行錯誤の末に釣れた一匹は、何物にも代えがたい価値がありますよ!
月明かりや風が釣果に与える影響
夜アジングの釣果は、潮や時間帯だけでなく、月明かりや風といった天候要因にも左右されます。
月明かりの影響
一般的に、満月の夜はアジングには不向きと言われることがあります。
その理由は、月明かりで海中が明るくなりすぎると、常夜灯の効果が薄れてアジが広範囲に散ってしまい、ポイントが絞りにくくなるためです。
また、アジの警戒心も高まる傾向にあります。
しかし、満月でも釣れないわけではありません。
月明かりが直接当たらない堤防の影(シェード)や、ストラクチャーの際などを狙うことで、アジが潜んでいる可能性は十分にあります。
月夜は釣りにくいというセオリーを理解した上で、狙い方を工夫することが大切です。
風の影響
風はアジングにおいて厄介な存在です。風が強いと軽いジグヘッドが飛ばず、ラインが風に流されて操作が難しくなります。
しかし、風を味方につけることも可能です。
風が岸に向かって吹く「向かい風」の場合、プランクトンが岸際に寄せられるため、アジの活性が上がることがあります。
少し重めのジグヘッドで対応しましょう。
逆に岸から沖へ吹く「追い風」の場合は、軽いジグヘッドでも遠投しやすくなるメリットがあります。
風向きと強さを考慮して、立ち位置や仕掛けを調整しましょう。
風が強い時の対策
- 風裏になるポイントを探す
- ジグヘッドを少し重くして操作性を上げる
- ロッドティップ(竿先)を海面に近づけて、ラインが風を受ける面積を減らす
快適な夜アジングを楽しむために
夜のアジングは、日中とは違った魅力と戦略性があり、一度ハマると抜け出せない奥深い釣りです。この記事で解説した基本とテクニックをマスターすれば、あなたの釣果はきっと向上するはずです。最後に、快適で安全な夜アジングを楽しむための要点をまとめます。
- 夜はアジの餌となるプランクトンが常夜灯に集まりポイントが絞りやすい
- アジの警戒心も下がるため夜はアジングのゴールデンタイムとなる
- 場所選びは常夜灯の明暗部や潮通しの良い堤防の先端が基本
- 仕掛けは1g前後のジグヘッド単体リグから始めるのがおすすめ
- ワームはクリア系・グロー系・ソリッド系の3種を状況に応じて使い分ける
- 安全確保のためヘッドライトは必須、赤色ライトも活用する
- 集魚灯は有効だがルールを守りプランクトンパターンに注意する
- 釣行前にはタイドグラフで潮の動きとマズメ時を確認する
- アジのいるレンジはキャスト後のカウントダウンで探る
- 常夜灯なしのポイントでは潮通しを意識しランガンスタイルで攻める
- ラインが見えない時は視認性の高いラインやグロー系ワームが有効
- 釣れない時はアクション・ワーム・リグをとことん変えて試行錯誤する
- 満月の夜はシェードを、風が強い日は風裏を狙うなど天候も考慮する
- ライフジャケットを必ず着用し、足場の安全を確認する
- ゴミは必ず持ち帰り、釣り場の美化に努める